ロボットはどうやって動く?センサーとモーターのひみつを解説
ロボットはどうやって動いているのでしょうか?
「電気で動いてる?」「プログラムで命令してる?」と、気になる子どもたちも多いはずです。
この記事では、ロボ団高崎校で使っているLEGO® Mindstorms EV3を例に、
ロボットの動きの仕組みをわかりやすく解説します。
ロボットが動くために必要な3つの要素
ロボットは大きく分けて、次の3つの力で動いています。
- ① モーター:ロボットの「筋肉」
- ② センサー:ロボットの「目や耳」
- ③ プログラム:ロボットの「頭(考える力)」
この3つがそろうことで、ロボットは「自分で動いて考える」ようになります。
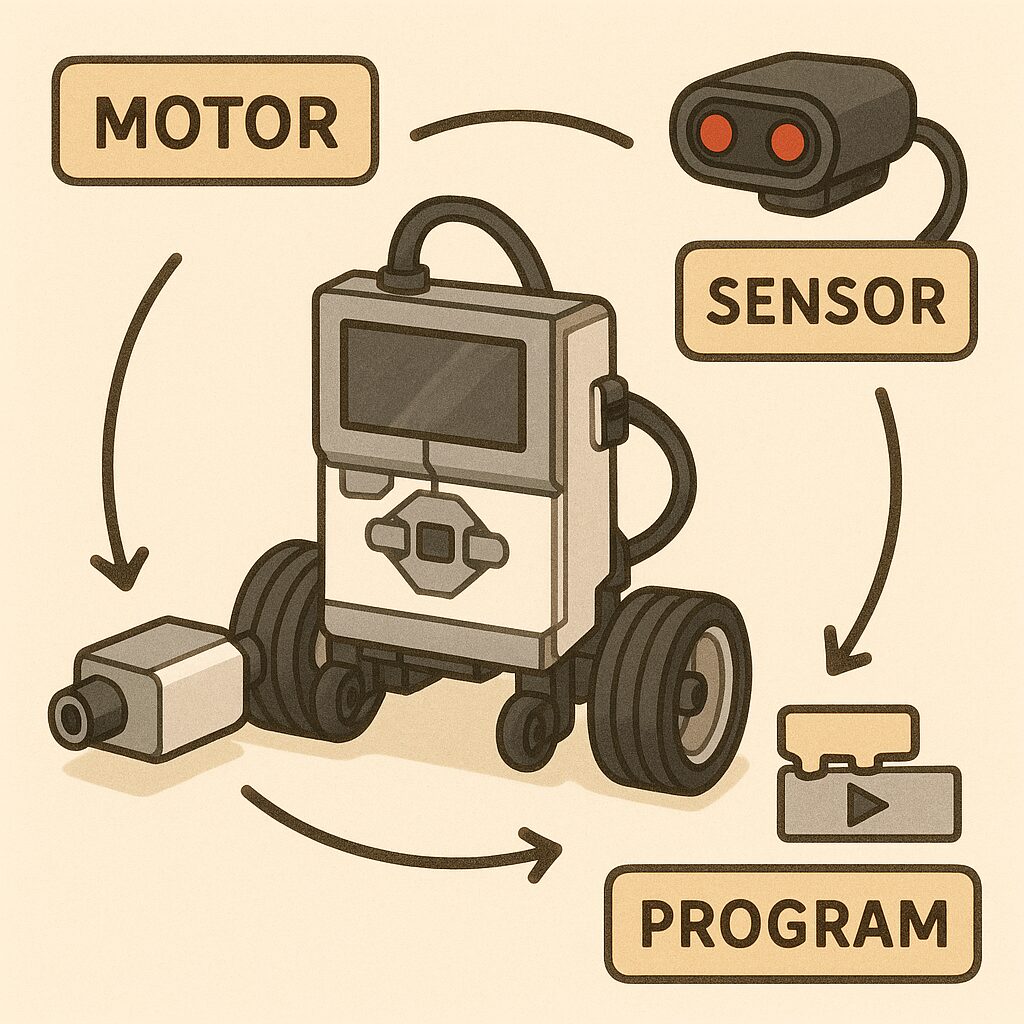
① モーター:ロボットの「筋肉」
モーターは、ロボットを実際に動かすための部品です。
ロボ団で使うEV3には、大きなモーター(Lモーター)と小さなモーター(Mモーター)があります。
- Lモーター:ロボットの車輪を回して前進・後退
- Mモーター:アームやハンドなど、細かい動きを担当
たとえば、「前に進む」「右に曲がる」などの命令は、
モーターを回す回転数とスピードをプログラムで決めているのです。

つまり、モーターはロボットの筋肉のような存在。
「動け!」という命令を出すのがプログラムで、その力を発揮するのがモーターです。
② センサー:ロボットの「目」や「耳」
ロボットが「考えて」動くためには、周りの状況を感じ取る力が必要です。
それを担当しているのがセンサーです。
ロボ団高崎校で使うEV3には、次のようなセンサーがあります。
- カラーセンサー:黒や白、赤などの色を見分ける
- 超音波センサー:前にある物との距離を測る
- タッチセンサー:押されたことを感知する
- ジャイロセンサー:角度や回転を検出する

たとえば、黒い線を見つけたら止まるプログラムを作ると、
ロボットはまるで目で見て判断しているように動きます。
センサーがあることで、ロボットは周りの情報をキャッチし、
人間のように反応できるようになるのです。
③ プログラム:ロボットの「頭(考える力)」
最後に、ロボットに「考える力」を与えているのがプログラムです。
プログラムとは、ロボットに対して出す命令書のようなもの。
どんな動きをするか、どんな条件で止まるかを、順番に指示していきます。
- 「前に進む」→「黒を見たら止まる」→「右に回る」
- 「超音波センサーが物を見つけたら後退する」
ロボ団の授業では、ブロックを並べるだけでプログラムが作れる
ビジュアルプログラミングを使っています。
初めてでも直感的に理解できるので、小学生でも安心です。

ロボットが動くしくみをまとめると?
ロボットの動きをまとめると、次のようになります。
センサーが情報を集める → プログラムが考える → モーターが動く
この3つの力が連携しているからこそ、ロボットはまるで生きているように動くのです。

ロボ団高崎校の体験会で「動くしくみ」を体感!
ロボ団高崎校では、体験会で実際にロボットを作って・動かして・考えることができます。
- センサーで線を見つけるロボットを作る
- プログラムで「前進→停止→回転」を設定
- 動きを見ながら何度も修正し、思い通りに動かす
この体験を通して、子どもたちは自然に「考える力」や「試す楽しさ」を身につけます。
🚀 体験会に申し込む
ぜひ、親子でロボットの“ひみつ”を体験してみてください!
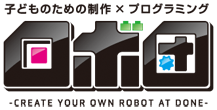



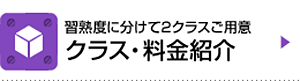
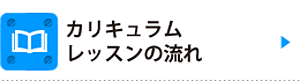
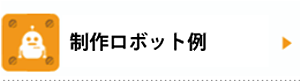
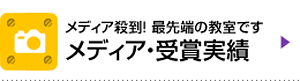
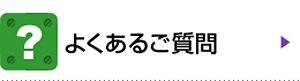

この記事へのコメントはありません。